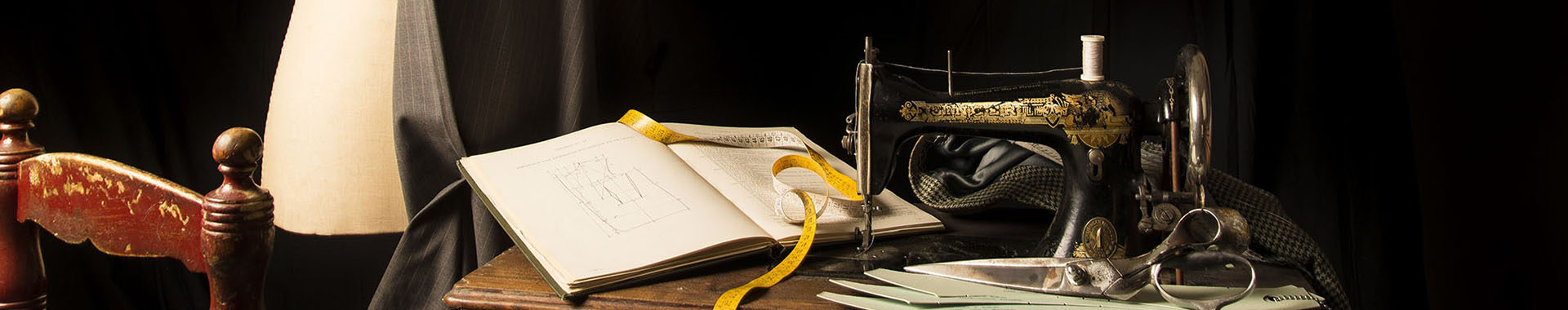近年、個人でアパレルブランドを立ち上げ起業する人が増えています。
個人アパレルブランドを始める場合、法人とは設定する目標や予算、やるべきこと等が異なります。
また、アパレル業界が未経験の場合は何から進めればよいのか分からなかったり、意外と複雑で細かな工程が多いため自分一人では難しいと感じる点も多いでしょう。
そこで今回の記事では、初心者の個人がアパレルブランドを起業するために知っておきたいこと、流れ、サポートしてくれるおすすめのサービスについて解説してまいります。
ぜひ最後までご覧いただき、参考にしていただければと思います。

個人アパレルブランドの法人との違い
アパレルブランドを個人で立ち上げる場合と法人として立ち上げる場合、主に「売上予算」「広告予算」「ターゲット」「在庫数」といったカテゴリーに大きな違いが表れます。
法人の場合、数億円~数十億円以上の売上の獲得を目標とするため、それに伴い在庫数や在庫金額は大きくなります。工場に大量の製造を依頼するため単価は下がります。
また、幅広いターゲットに対してさまざまな広告を実施し、より多くの人に商品やブランドを知ってもらうために宣伝を行います。
一方、個人アパレルブランドの場合は、売上予算は数十万円~数百万円。法人と比べて持てる在庫数が少ないため小ロットの発注となり製品の単価は高くなります。
広告予算も大きくないため、よりターゲットを絞りニッチな市場に向けて販売する傾向にあります。
個人アパレルブランドの販売方法
個人でアパレルブランドを起業する場合、販売するスタイルは大きく分けて実店舗かネットショップ・ECサイトでの展開となるでしょう。
他にも細かいものだとフリーマーケットやポップアップストアへの出店等もありますが、継続して販売する場合は実店舗かオンラインでの販売、あるいは二つの併用という形になります。
それぞれの特徴は以下となります。
実店舗
実店舗でビジネスを展開する場合、お客様と対話しながら直接商品を見て触れる機会や試着などの体験を提供することが可能です。
やはり手にとって素材や生地、縫製の品質を確認し、サイズや着心地等を確認した上で購入したいと考えるお客様は多く、また実店舗があることでブランドに対する信頼性も増すため、いまだにその存在価値は大きいと言えます。
しかしコンセプトやターゲット、立地を考慮した物件選びをする必要や毎月の家賃の負担は大きく、高い初期費用や運営コストがかかるという点はデメリットでしょう。
ネットショップ、ECサイト
最近のショッピングの主流にもなっているネットショップやECサイトは、個人でアパレルブランドを立ち上げる人にとって第一選択肢となるでしょう。
というのも広範囲の顧客にアクセスが可能で、更に低コスト・低リスクでスタートできるという大きなメリットがあるためです。
広告やプロモーションにInstagramを始めとしたSNSを上手く活用することで、こちらも費用をあまりかけずに販売へとつなげることが出来ます。
最近は商品を仕入れ「BASE」や「メルカリ」等を利用して手軽にアパレル販売を行ったり、「Amazon」や「楽天」にショップを開く方法も人気です。
無料で開設し商品が売れた時だけ手数料を支払うという仕組みのプラットフォームが多いため、十分な資金がなくてもアパレルショップを立ち上げることが可能です。
実店舗とネットショップにはそれぞれメリット、デメリットがあります。ブランドのターゲットや資金をしっかり考慮した上で無理し過ぎず、自身に合ったスタイルを選びましょう。
個人アパレルブランドの立ち上げに必要な準備
次に個人でアパレルブランドを起業する際の具体的な手順を以下に紹介していきます。
全体の流れを把握し、事前に準備しておくもの等をチェックしておきましょう。
1.ブランド名を決める
ブランド名を決める時には、他のブランドやサービスの名前に同じものがないか確認することが重要です。
特に、既に商標登録されている名前を使ってしまうと商標権の侵害となり使用できなくなってしまうため、必ず前もって同様の名前がないかを検索したり調べておきましょう。
そしてオリジナルのブランド名が決定したら商標登録をしておくことをおすすめします。
2.開業届を提出する
個人アパレルブランドを立ち上げるということは個人事業主としての開業になるかと思います。
この場合、開業届を提出しましょう。必須ではありませんが、届出をすることで青色申告が出来るようになりますし、屋号(ブランド名)で銀行口座を開設することも可能となります。
3.商品の準備
いよいよ商品の準備ですが、仕入れるのか生産するのかによっても大きく異なります。
生産する場合は縫製工場を探して契約しますが、個人の場合は小ロットでの製造からスタートすることになるかと思うので、対応してくれる工場を探さなくてはなりません。
その際は後で紹介する「縫製屋ドットネット」のサービスがおすすめです!
販売する商品が完成したら、ネットショップに掲載するための写真を撮影します。
魅力が伝わる写真を用意すること、またモデルの着画を載せることもおすすめです。
サイトへ写真の登録をしたら、服やアイテムの情報と魅力が分かりやすく伝わるような文章を作成しましょう。
4.決済・配送方法を決める
今はさまざまな決済方法がありますが、出来るだけ幅広く対応することで購入してもらえるチャンスが増えます。
商品は購入したいけれど決済方法に対応しておらず購入を断念するケースも意外と多くあるためです。
ただし、管理コストもかかるためいきなり網羅するのではなく、ブランドの成長に合わせ徐々に追加していくというやり方が良いでしょう。
配送については宅配業者の選定を行い、有料で急ぎの発送や時間指定、代引きに対応する等のオプションをつけるとユーザーに親切です。
5.カスタマーサポートの設置
お客様からの問合せや質問に対応する窓口の準備も忘れずに準備しましょう。
問い合わせフォームや対応が可能なら専用の電話番号を用意して明記しておくことでお客様に安心して買い物をしてもらうことが出来ます。
個人アパレルブランドの立ち上げにはいくらかかる?
個人のアパレルブランドの立ち上げにはいったいどれくらいのお金がかかるのかという点も気になることかと思います。
費用の相場は以下の通りです。
実店舗
実店舗を持つ場合、店舗の敷金、礼金、不動産会社の仲介手数料、家賃、改装費、設備購入費、仕入れ・製造代金、広告宣伝費etc…を含め、約1000~1500万円の費用が相場としてかかります。
もちろん立地や店舗の規模、内装工事の内容によっても異なります。
ネットショップ
ネットショップの場合は商品の仕入れ資金または製造代金、ショップの開設費、運営費として数万円~数十万円程度に抑えられます。
ショップの開設費は無料のところも多いです。
以上のように、実店舗とネットショップではお金の面でかなりの差がありますね。
資金が足りない場合は「クラウドファンディング」を利用する方も増えています。
個人アパレルブランド、成功のポイントは?
個人アパレルブランドを立ち上げるには特別な資格や経験は必要ありません。
しかし売上を出して安定して運用していくためにはいくつか注意しなければならないポイントがあります。
せっかくのブランド立ち上げを失敗で終わらせないために、ぜひチェックして下さいね。
コンセプトとターゲットの明確化
アパレルブランドに限らず、何か新しい事業を始める際にはそのコンセプトとターゲットを細かく明確にすることが非常に大切です。
コンセプトが決まっていないと展開する上でブレが発生し、消費者にとっても売る側にとってもどんな店なのか分からず混乱します。
またターゲットも同様で、例えば「20代 女性」といったようにざっくりしたものにしてしまうと、学生向けなのか社会人向けなのか、カジュアルなのかフォーマルなのか、どこの誰に向けた商品なのかまったく定まりません。
ターゲットは幅広い方が良い、というイメージを持っている人も意外と多いのですが、逆にファンやリピーターが得られにくくなってしまうのです。
ニーズやトレンドも調査しながら、どんなブランドを作りたいのかしっかりと検討して決めていきましょう。
Webを活用した集客
今の時代、新たな情報やサービスはテレビや雑誌ではなくSNSやネットで知る、という人が多くなっています。
実際に多くのブランドがオンラインショップを持っており、さまざまなSNSにアカウントを作成して投稿しています。
いくら素敵な商品を揃えていても、たくさんの人に認知されなければ意味がありません。
そのため、集客するためはSNSや動画といったWebで行うマーケティングの知識を身に着けることも成功へのポイントとなります。
丁寧な接客
最近はサービスの利用や商品の購入の決め手として「口コミ、評価、レビュー」を参考にされる方がほとんどです。
その中で顧客への対応が不適切な場合クレームにつながる可能性が高く、顧客の満足度は大きく低下します。
「この店で購入すると嫌な思いをするんだな」という印象を持たれてしまいそのことが発信されてしまうと、想像以上に拡散され経営が続けられなくなってしまうという事態に陥ることもあるのです。
そのため、一人ひとりのお客様を大切に、丁寧で誠実な対応を心がけることは起業する上でとても大切なことです。
シェアオフィス、バーチャルオフィスの利用
アパレルブランドを起業する場合、「特定商取引法」によりネットショップに住所を表示しなくてはなりません。
しかし個人アパレルブランドの場合、事務所や店舗を持たない人が多くいます。
自宅の住所を掲載してしまうと悪用されてしまう可能性もあり、リスクが伴いますよね。
そのため、最近はバーチャルオフィスと呼ばれる事業用に住所を貸し出してくれるサービスがありますので、これらを活用することをおすすめします。
縫製屋ドットネットは個人アパレルブランドの起業を支援します
以上で紹介した内容は個人アパレルブランドの立ち上げに必要な作業のほんの一部です。
ネットショップでの販売であれば簡単に始めることは出来ますが、自社の洋服を作る場合は初めての人にとって難易度が上がります。
特に初心者で小ロットの製造を受けてくれる縫製工場を探すことは、説明も上手くできず苦労するでしょう。
「ファッションが好き」という気持ちは一番大切ですが、それだけでブランドを運営していくことは出来ないのです。
そこでおすすめしたいのが当社「縫製屋ドットネット」のサービスです。
縫製屋ドットネットでは、洋服を作りたい人と日本国内の縫製工場をマッチングさせるサービスを提供しており、初心者や個人の方も歓迎しています。
高い技術力と豊富な実績、ノウハウ、ブランドの立ち上げに関連する専門の知識を持った信頼できる工場ばかりなので、相談しながら安心して進めることが出来ます。
個人アパレルブランドの実現に向け、まずは気軽にお問合せいただければと思います。